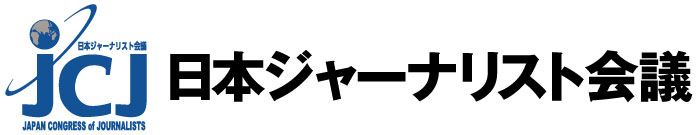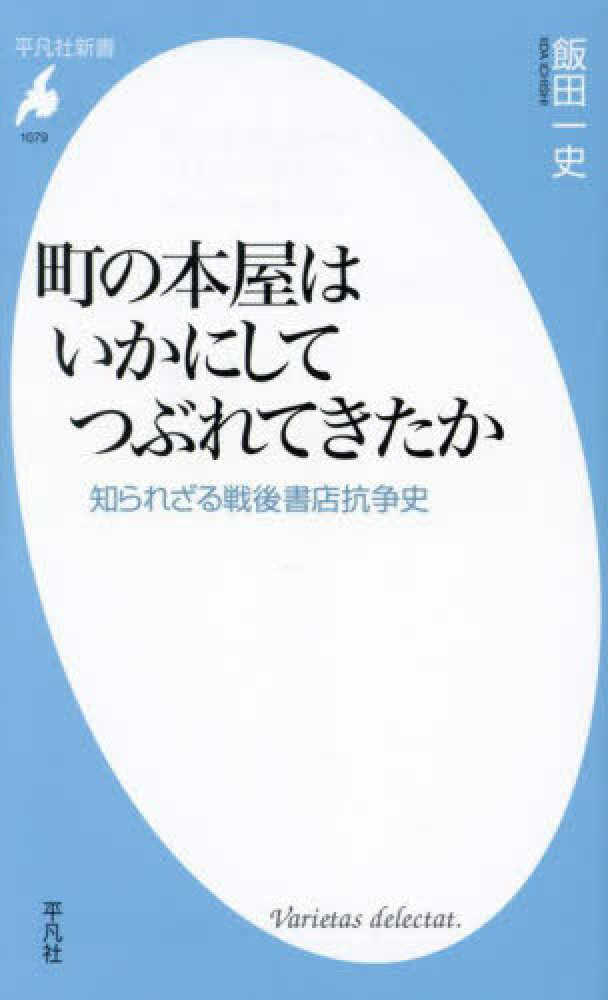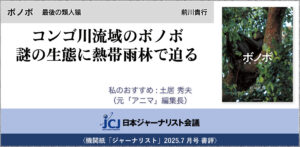〈2025.7月号 緑蔭特集〉飯田 一史(著)『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか──知られざる戦後書店抗争史』 ・・・10年スパンで遭遇する出版界のビッグイシュー 私のおすすめ:池田 隆(元出版取次店 勤務)
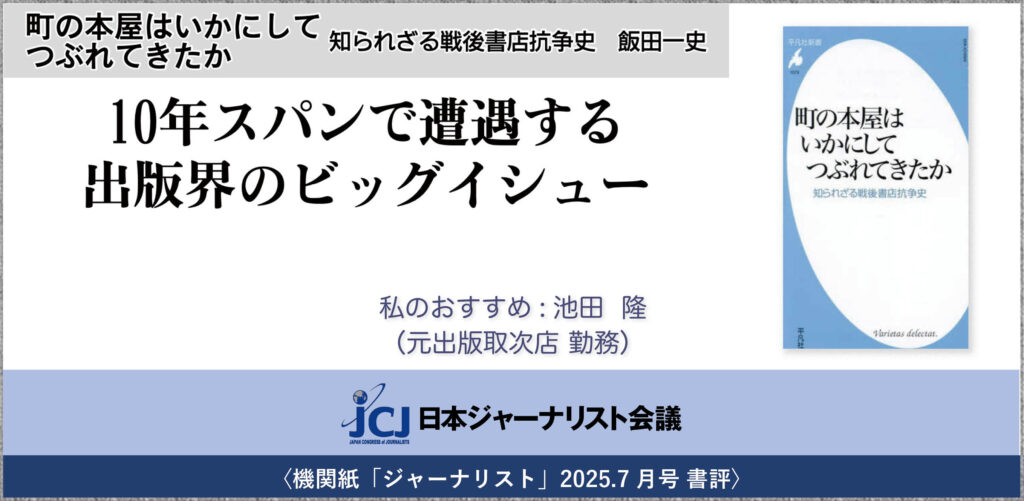
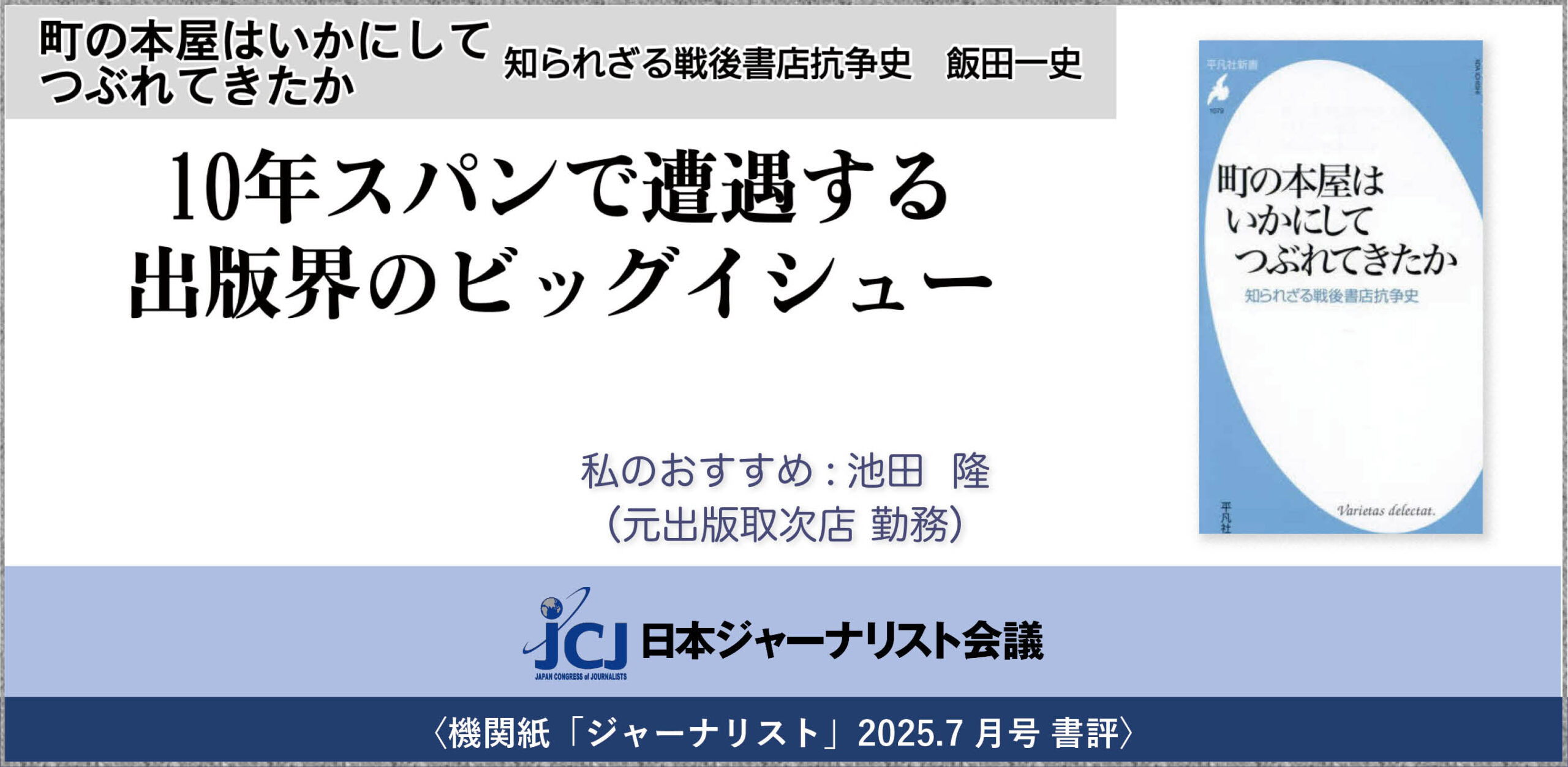
読み終えて脳裏に浮かんだのは、1990年代の出版業界が好景気で浮かれ、遅れたバブルを謳歌していると揶揄されていた頃だ。採算など無視の新規出店が毎月30店以上、その陰でつぶれる本屋も毎月30店を超え、配本先書店一覧表の書き換えに追われていた。
特に評者が出版業界の分岐点となったと思うのは、1970年代「ブック戦争」は、1990年代の「須坂構想」、2000年代の「Amazonの日本進出」である「ブック戦争」は1972年に日本書店商業組合連合会(日書連)が行った加盟書店1千店の調査から人件費高騰・経営逼迫店が大半を閉めと判断。取引条件の改訂を、出版社と取次店に要望した。
その実現のため、特定の出版社の本を棚から外すという、出版史上で初めての小売書店による13日間のストライキを決行した。その結果、取引条件の改善は実現したが、覚書きで交わされた「責任販売制の実施」は、具体的な取り組みがなく放置された。
「須坂構想」は、長野県須坂市に述べ6万㎡の出版流通の巨大基地を設け、1990年代当時、業界が抱えていた諸課題を一挙に解決しようとした大プロジェクト。だがこれもまた各業界の思惑が錯綜して、十分な機能を発揮できず頓挫してしまった。
21世紀初頭の「Amazonの日本進出」は、結果的には書店が求めていた改善・要望の大半を、3年間で解消・解決してしまったと뗆、本書は述べる。
さらに出版業界は「雑誌と書籍の一体流通・取次寡占・再販契約」で成長してきたが、今や、それが改善の阻害要因になってはいないかと、本書は指摘している。(平凡社新書 1,320円) 池田 隆(元出版取次店 勤務)