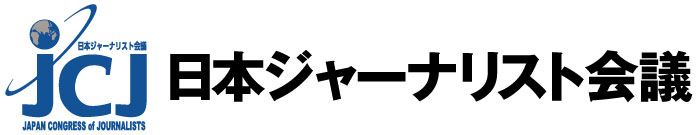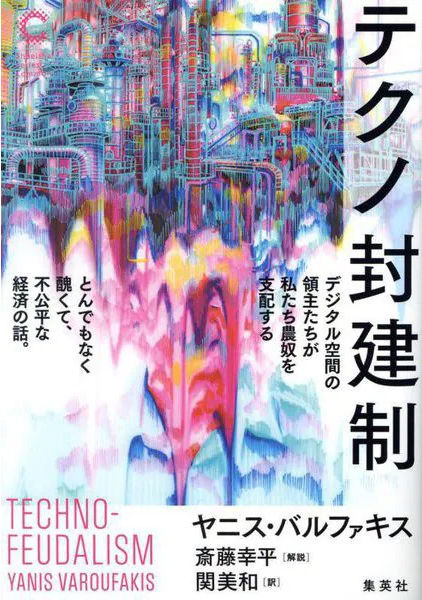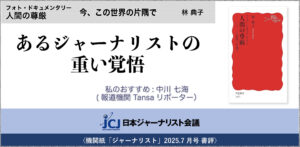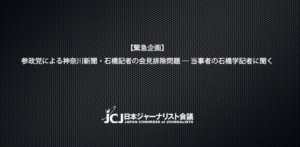〈2025.7月号 緑蔭特集〉ヤニス・バルファキス (著)、斎藤 幸平 (解説)、関 美和 (翻訳)『テクノ封建制 ──デジタル空間の領主たちが私たち農奴を支配する とんでもなく醜くて、不公平な経済の話。』・・・「個人の自律」を侵すテクノ封建主義 私のおすすめ:内田 聖子(アジア太平洋資料センターPARC共同代表)
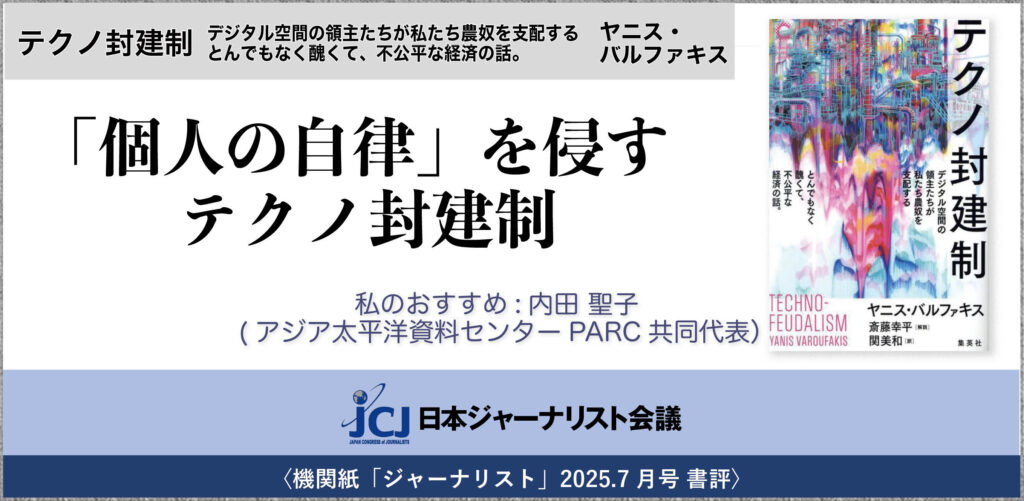
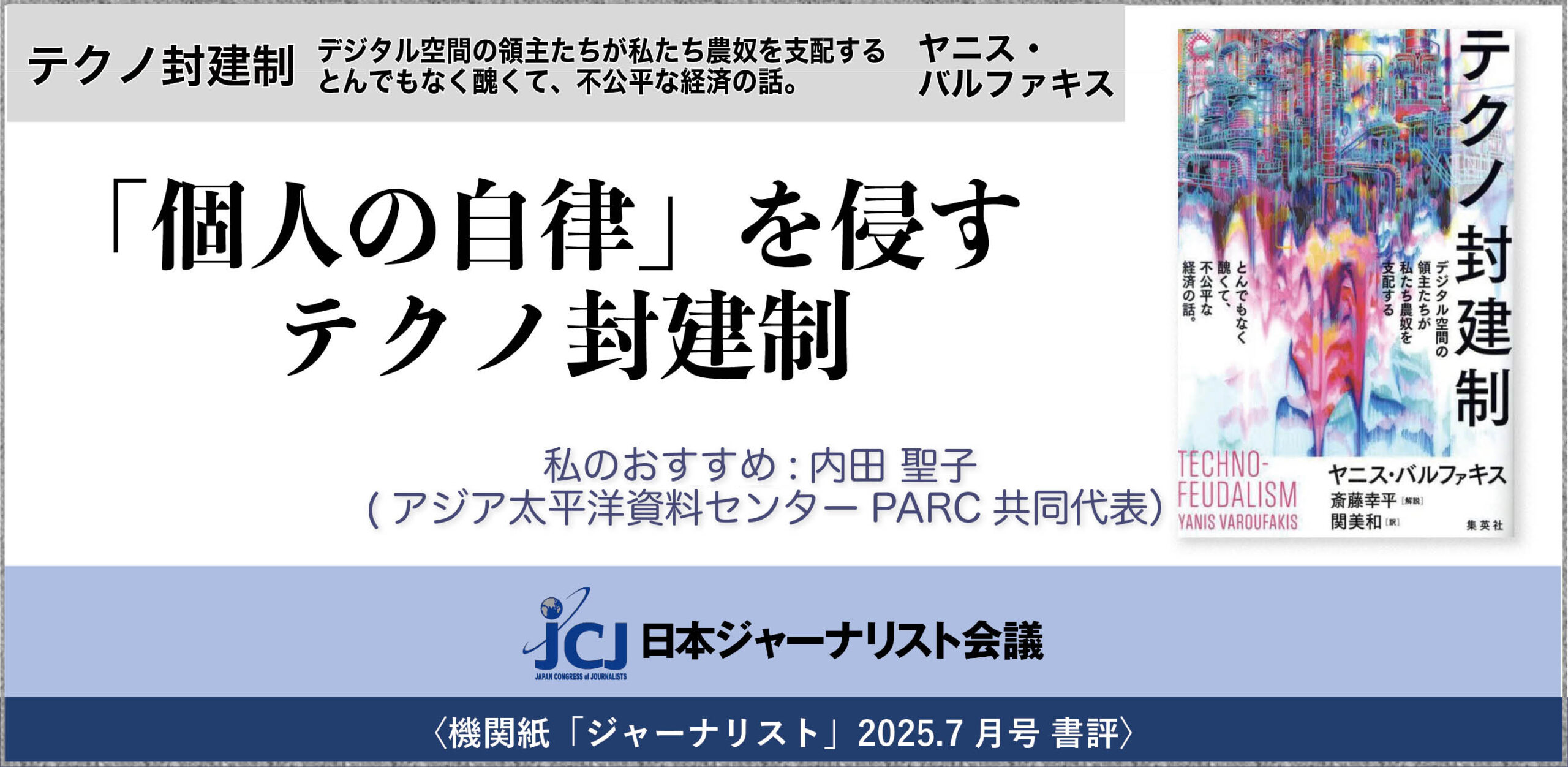
インターネットは資本主義のあり様を根本から変え、破壊的で搾取的なシステムを作り上げた。これは 進歩なのか?
ギリシャ生まれの「異端の経済学者」、ヤニス・バルファキス『テクノ封建制──デジタル空間の領主たちが私たち農奴を支配する とんでもなく醜くて、不公平な経済の話。』 (関美和訳 集英社)は、 若き日に父と交わした会話に応える形で、資本主義の醜悪な変容の本質を解題していく。
ブレトンウッズ体制崩壊後、資本主義の権力は経済圏から金融圏へ、つまり工業や商業から投資銀行家の世界へと移行した。その決定的な要因が、コンピュータの出現だ。金融商品は複雑化・高速化して取引市場に投げ出され、人々の暮らしとは無関係の莫大な投機マネーが世界をかけめぐった。
その後に訪れるのが「テクノ封建制」だ。イ ンターネットは新しい形の資本を育て、その所有者たちが新たな支配階級となった。「クラウド資本」が、土地や 生産手段を持たない「農奴」―スマホやパソコンを通じて、24時間クラウド資本に縛り付けられる私たち―に対し圧倒的な力を持つ。
個人情報や行動履歴を収集し、私たちの行動を予測・操作するビッグテックのビジネスモデルは、すでに「監視資本主義」として批判されてきたが、改めて資本主義崩壊の中にそれを位置付けたことが本書の傑出した点だ。
テクノ封建制から「個人の自由と自律」を救うためには、生産・流通・協働・コミュニケー ション手段の所有権を根本から構成しなおす必要がある。途方もない道のりだが、その鍵は「民主化された企業と貨幣」、そして「共有財としてのクラウドと土地」だと著者は論じる。
私はテック労働者による集団行動や倫理的な技術をめざす研究者、そして草の根の市民による運動にそれを期待する。世界の市民社会は、すでにテクノ封建制と果敢に闘い続けている。まずは日々ネット上で購買やSNSを行うその一瞬一瞬にも、私たちは「農奴」 であるという現実を冷静に受け止めることから始めなければならない。 (集英社 1,980円) 内田聖子(アジア太平洋資料センターPARC共同代表)