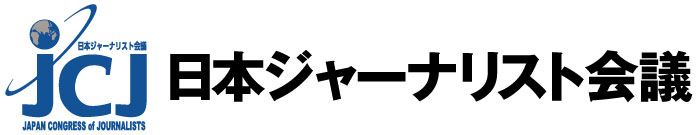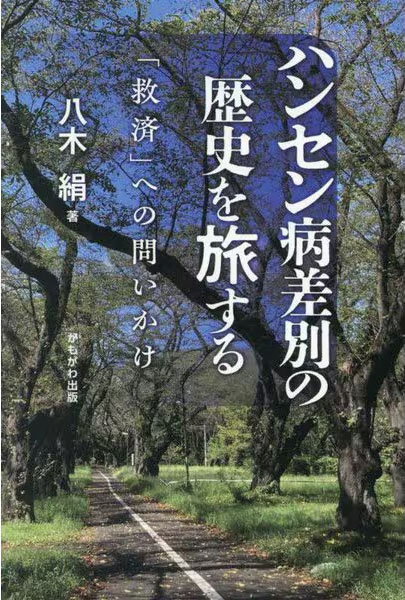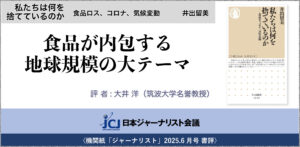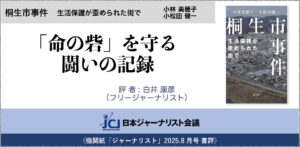〈2025.8月号 書評〉八木 絹(著)『ハンセン病差別の歴史を旅する ──「救済」への問いかけ』・・・差別の事実と向き合い「救済」への歩みを辿る 評者:霜村 三二(元都留文科大学講師)
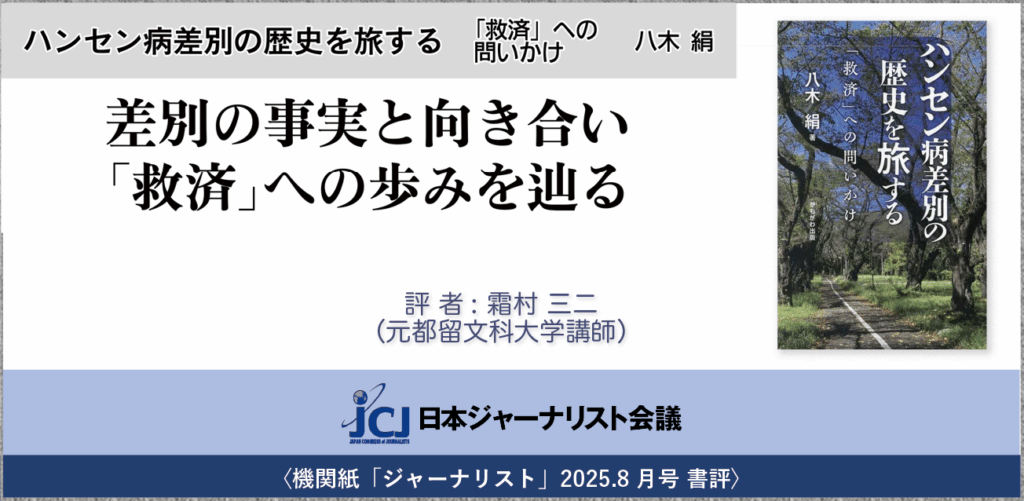
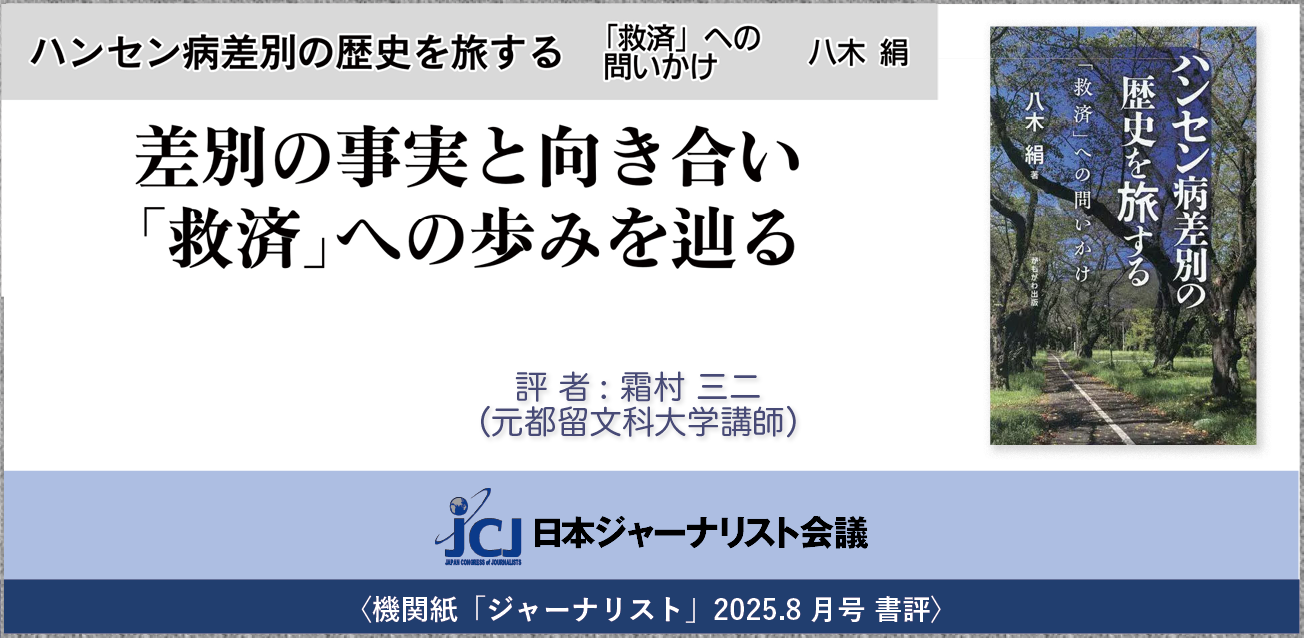
「ハンセン病差別の歴史を旅する」という著者の呼びかけに、私はどう答えたらいいのか。差別の事実と向き合うときの「驚き」「憤り」という 感情を丁寧に深く追うことを「歴史を旅する」と 表現した著者の真っ直ぐな言葉が迫る。
日本のハンセン病差別は、歴史の中でも最大の差別事案であり、家族までにも人生被害を与えてきた。それにもかかわらず、重大な人権問題として日本社会には広く共有されてはいなかったことが、顕わになったのがコロナ禍での感染症差別だった。こんなにも簡単に差別感情が広く振りまかれるなどとは。
私はハンセン病療養所多磨全生園の傍に住み、若い人たちをハンセン病資料館に案内してきた。熊本での「黒髪校事件」 は伯父が一方の関係者(入学賛成派代表)だったこともあり、授業では教育の在り方として何度も取り上げ、差別の不当さを語ってきた。
しかし、差別に加担した不正義を衝くことだけでよかったのか。それは深い思考とは対極にあったのではないか。著者が「ハンセン病問題〈から〉学ぶ」と指摘した今を生きる、そこにつながる学びこそ、「旅する学び」 である。ハンセン病施設で暮らす元患者の平均年齢は、90歳近くになっている事情、ハンセン病差別を「知らない」と言う人が多数になり、このままではハンセン病問題は無かったことになる。
本書で著者は、救済に尽くした宗教者たちの行動の心根を深く旅する。「差別の歴史から学び、そこから自由になる方向を問い続けたい」「一緒 に旅をしてくださる方を」という筆者の言葉に心惹かれる私も伴走者として生き、旅をしたい。(かもがわ出版 1,800円) 霜村 三二(元都留文科大学講師)