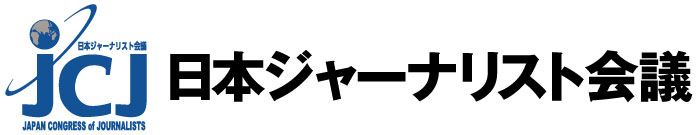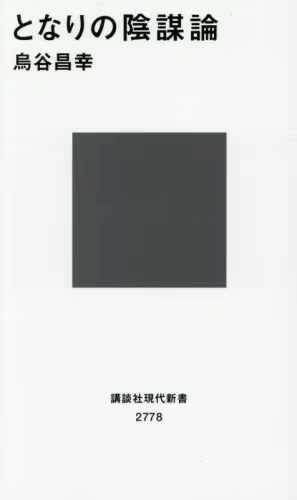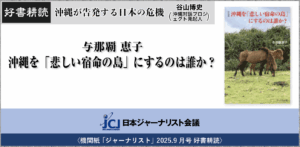〈2025.9月号 好書耕読〉烏谷 昌幸(著)『となりの陰謀論』・・・国際政治をも動かす陰謀論 選者:岩下 結(「本屋とキッチンよりまし堂」店主)
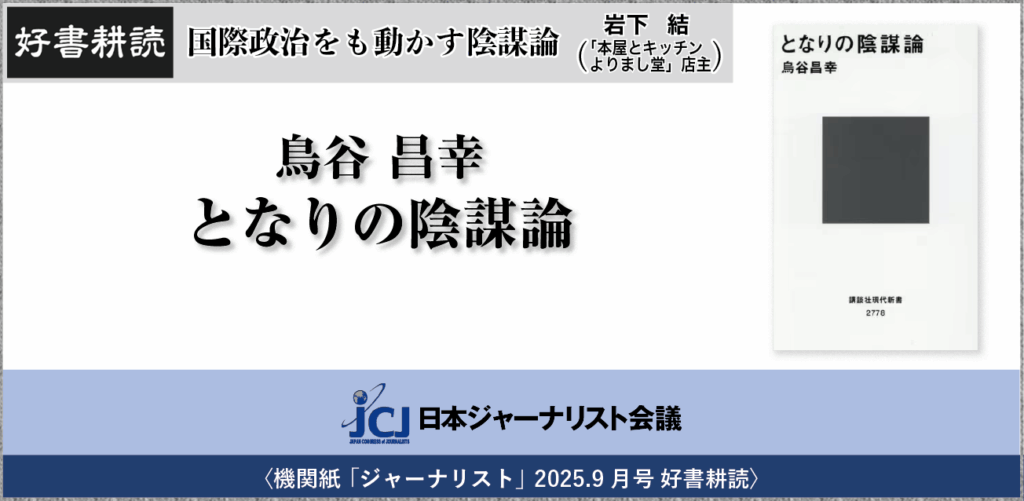
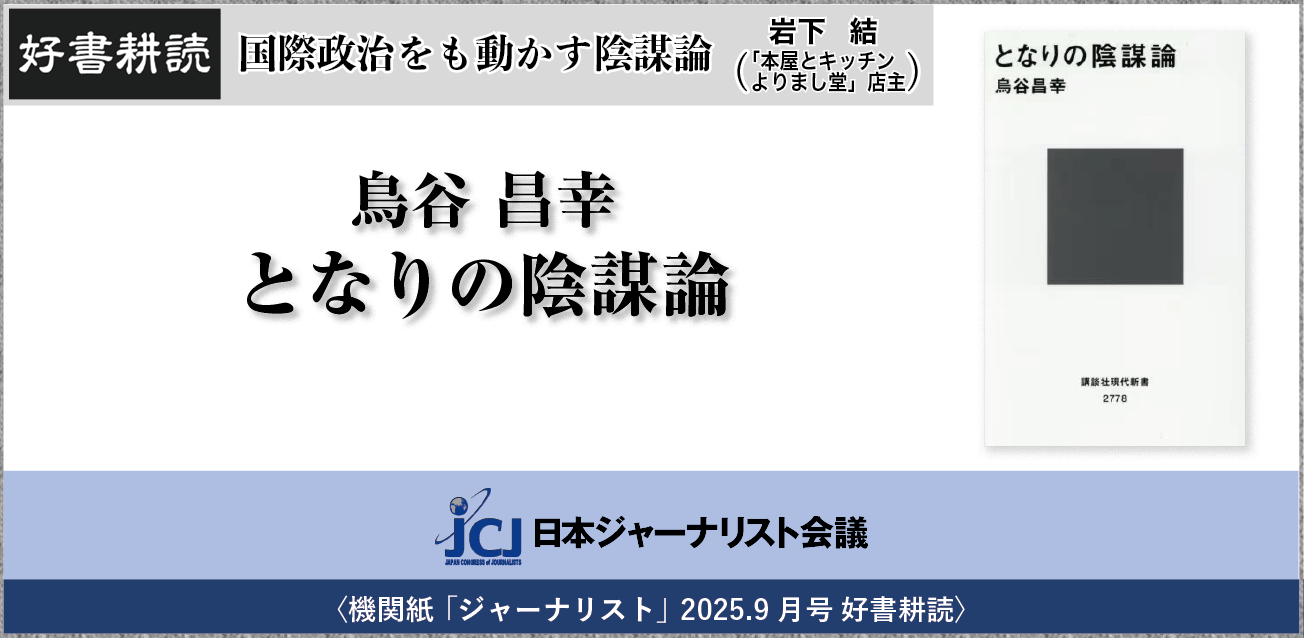
参院選における参政党の躍進は、多くの市民を戦慄させた。それは彼らの極右的主張のみならず、荒唐無稽な陰謀論や似非科学(「メロンパン」 から「文化マルクス主義」まで)を公然と語り、メディアやSNS上で、どれほど否定されても動じない様に、異様さを感じたからであろう。
陰謀論や似非科学は以前から存在した。とりわけコロナ禍以降、ワクチン懐疑論やマスク不要論を通じて、政治的志向を持たないように見えた隣人が、突然陰謀論を語り始める恐怖を、多くの人が経験しているはずだ。
そうした危機感に対応したタイムリーな書が、烏谷昌幸『となりの陰謀論』(講談社 現代新書)である。著者は、 陰謀論に陥る人を情報弱者扱いするのではなく、誰にもある認知的バイアスの帰結と捉える。とりわけ「世界をシンプ ルに解釈したいという欲望」 と「大切な何かが奪われる感 覚」とが作用している。
いつの時代も陰謀論は存在したが、現在の危機は、それ を動員ツールとして活用する「陰謀論政治」が、国際政治を も動かす動因となったことである。
トランプ再来を招いたQアノンは、その代表格であり、日本でも無数の亜種を生んでいる。それは「移民による侵略」と いった排外主義言説と結びつき、民主主義社会を蝕む。非合理的な陰謀論を信じるか否かが、集団内で異論を排除する「踏み絵」として機能すると の指摘も重要だ。
陰謀論者はメディアや知識人を敵視し、否定されればされるほど、「マスコミは支配さ れている」との確信を強めて いく。
ではどうすればよいのか? 明確な処方箋はないが、終章で紹介されるフィリピンのドゥテルテ政権によるメディア攻撃を受けた記者らの例では、報道・法曹・学術・NGO等の 重層的ネットワークによって偽情報に対抗する道が示される。日本においても市民社会の総力で臨むべき喫緊の課題であろう。 (講談社 990円) 岩下 結(「本屋とキッチンよりまし堂」店主)