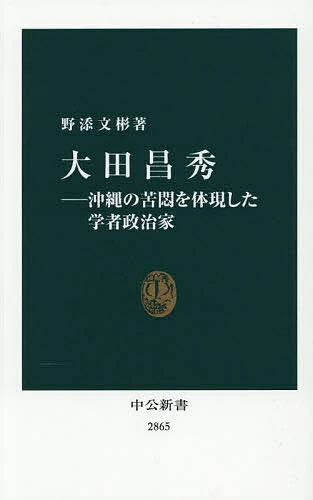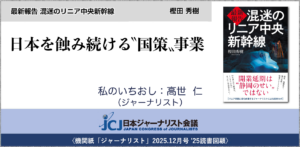〈2025.12月号 書評〉野添 文彬(著)『大田昌秀──沖縄の苦悶を体現した学者政治家』・・・国家と対峙せざるを得ない孤独と苦悩の生涯を追う 評者:鈴木 耕(編集者)
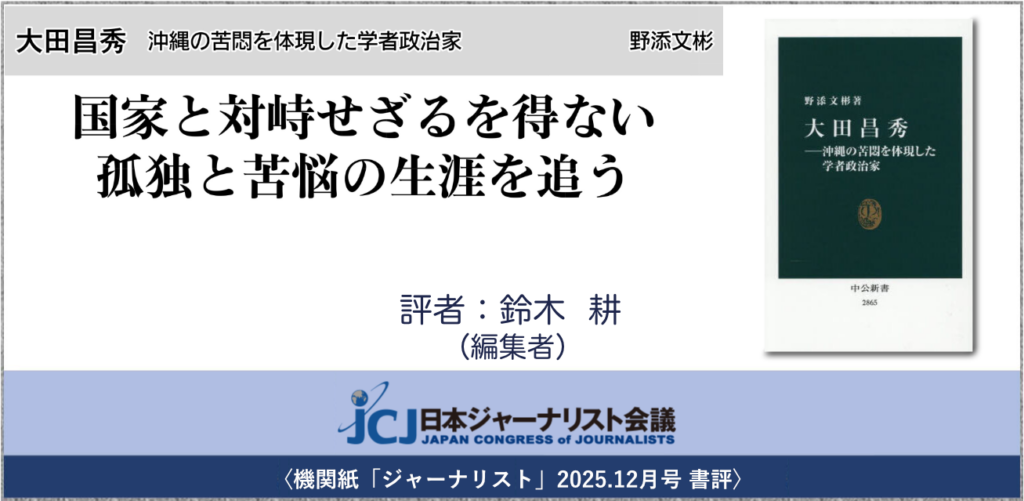
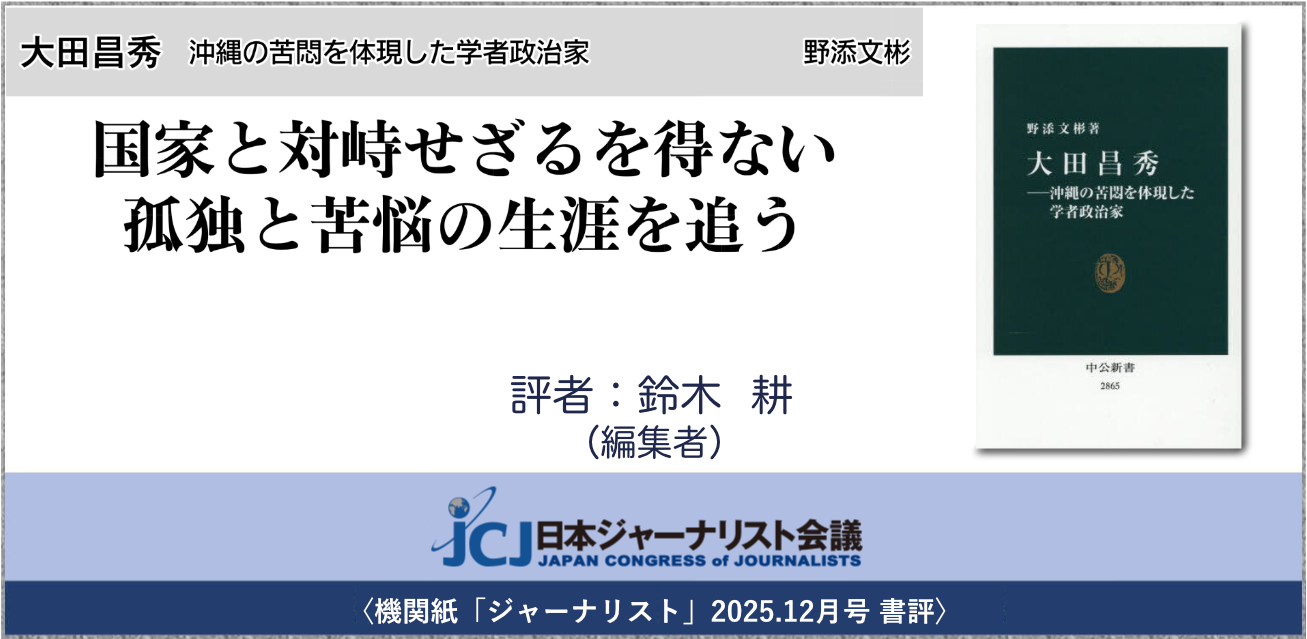
私はかつて、大田昌秀『沖縄、基地なき島への道標』(集英社新書)を編集したご縁で、大田さんとは親しくお付き合いさせていただいた。
私は毎年のように沖縄へ通っていたが、行くたびに誘われて酒席を共にした。私にとっての大事な人生の師であった。本書は、その大田さんの生涯を克明に辿り、初めて知ったことも多い得難い労作である。
大田昌秀さんは1925年6月12日、沖縄・久米島に生まれ、幼い頃から「秀才」の誉れが高かったが、貧困家庭に育ち、紆余曲折、沖縄師範学校時代には、沖縄戦に鉄血勤皇隊として駆り出され、生死の境をさまよった。
戦後、早稲田大学への「留学」を経て渡米、シラキュース大学院でジャーナリズムを学ぶ。彼の軌跡を辿れば、戦後を必死に生き抜いた若き学究の姿が見えてくる。
当初はジャーナリスト志望だっただけに、その感覚の鋭さは多くの学問的成果に生かされた。やがて琉球大学の教授として、沖縄の日本復帰運動に関わっていく。
沖縄に大田あり、と言われるほどの論客となり知事選に担がれ、彼の舞台は研究から政治へと急展開する。これが彼の生涯に影を落とす。やさしい人柄だったといわれる一方で、その頑固さには周りも手を焼いたとの評価もあった。それは国家と対峙せざるを得ない立場に立たされた者の孤独と苦悩の表出だった。
「戦争と平和」を最大の学問的・政治的課題として生き抜いてきた、学者政治家の残した「平和の礎(いしじ)」こそ、永遠の希望であり祈りである。2017年6月12日の死から3年後の7月、私は久米島に大田さんの墓を訪ねた。蝉しぐれが降る真夏の昼下がりだった。 評者:鈴木 耕(編集者) (中公新書 980円)