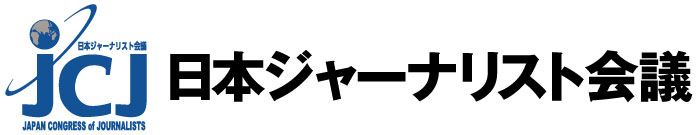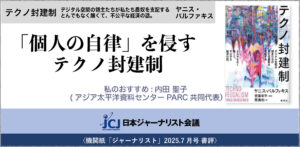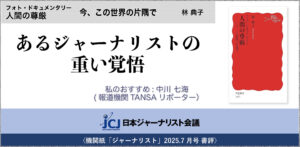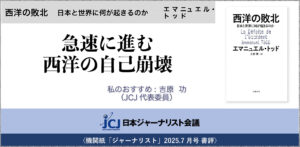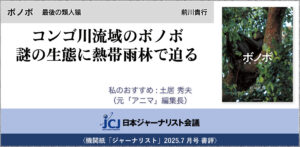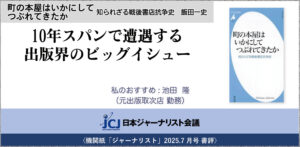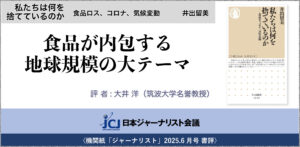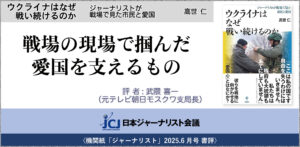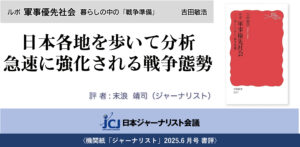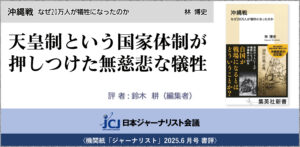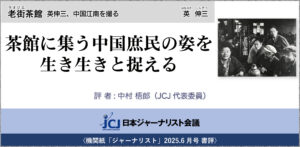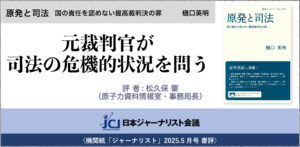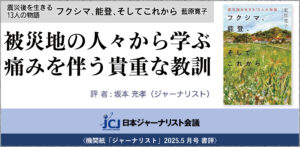〈2025.7月号 緑蔭特集〉ヤニス・バルファキス (著)、斎藤幸平 (解説)、関 美和 (翻訳)「テクノ封建制 ──デジタル空間の領主たちが私たち農奴を支配する とんでもなく醜くて、不公平な経済の話。」 ・・・「個人の自律」を侵すテクノ封建主義 私のおすすめ:内田聖子(アジア太平洋資料センターPARC共同代表) 新着!!
インターネットは資本主義のあり様を根本から変え、破壊的で搾取的なシステムを作り上げた。これは 進歩なのか? ギリシャ生まれの「異端の経済学者」、ヤニス・バルファキス『テクノ封建制──デジタル空間の領主たちが私たち農奴を […]
〈2025.7月号 緑蔭特集〉林典子 (著)「フォト・ドキュメンタリー 人間の尊厳──いま、この世界の片隅で」 ・・・あるジャーナリストの重い覚悟 私のおすすめ:中川七海(報道機関TANSAリポーター) 新着!!
私が所属する報道機関TANSAがニューヨークタイムスの取材を受けた際、林典子さんが、カメラマンとして、同道してきた。 後日、記事に載った写真に引き込まれた。TANSA編集長が、街路樹の下で立っている。報道機関の紹介だか […]
〈2025.7月号 緑蔭特集〉エマニュエル・トッド (著)、大野 舞 (翻訳)「西洋の敗北──日本と世界に何が起きるのか」 ・・・急速に進む西洋の自己崩壊 私のおすすめ:吉原 功(JCJ代表委員) 新着!!
「リベラルな世界秩序」ー実は米国を盟主とし、NATO諸国、日本、韓国を従えた帝国の世界支配は、音をたてて崩壊しつつある、との見解を首肯する人は、どのくらいいるだろう。 トランプ2の乱暴な政策に困惑はしても「民主主義・法 […]
〈2025.7月号 緑蔭特集〉前川貴行(著)「ボノボ──最後の類人猿」 ・・・コンゴ川流域のボノボ、謎の生態に熱帯雨林で迫る 私のおすすめ:土井 秀夫(元「アニマ」編集長) 新着!!
ボノボはチンパンジーに似ており、かつては動物学の世界でも、ピグミーチンパンジーと称され20紀に新種として認知されたゆえに、「最後の類人猿」とされる。 しかし、チンパンジーとボノボの生態は真逆といっていい。個体や群れの間 […]
〈2025.7月号 緑蔭特集〉飯田一史(著)「町の本屋はいかにしてつぶれてきたか──知られざる戦後書店抗争史」 ・・・10年スパンで遭遇する出版界のビッグイシュー 私のおすすめ:池田 隆(元出版取次店 勤務) 新着!!
読み終えて脳裏に浮かんだのは、1990年代の出版業界が好景気で浮かれ、遅れたバブルを謳歌していると揶揄されていた頃だ。採算など無視の新規出店が毎月30店以上、その陰でつぶれる本屋も毎月30店を超え、配本先書店一覧表の書 […]
〈2025.6月号 書評〉井出留美(著)「私たちは何を捨てているのか──食品ロス、コロナ、気候変動」・・・食品が内包する地球規模の大テーマ 評者:大井 洋(筑波大学名誉教授)
著者は栄養学分野で研究を重ね博士号を取った後に、食品ロス問題ジャーナリストとして活躍している。本書は文献や情報検索に基づく明確な文章で書かれ、説得力のある内容となっている。著者のこだわりだけで書かれた本ではない。 食品 […]
〈2025.6月号 書評〉高世 仁(著)「ウクライナはなぜ戦い続けるのか──ジャーナリストが戦場で見た市民と愛国」・・・戦場の現場で掴んだ愛国を支えるもの 評者:武隈喜一(元テレビ朝日モスクワ支局長)
ウクライナ停戦交渉を巡る情報が、メディアに溢れる。だが忘れてならないのは、今でも戦争が続き、市民の死傷者が続出していることだ。 本書は著者がウクライナの戦場を訪れ、ロケットランチャー部隊やドローン部隊、ロシア軍が残した […]
〈2025.6月号 書評〉吉田敏浩(著)「ルポ 軍事優先社会──暮らしの中の「戦争準備」・・・日本各地を歩いて分析 急速に強化される戦争態勢 評者:末浪靖司(ジャーナリスト)
本書は、米軍と自衛隊の一体化が進み、強化されている実態を分析し、この問題に関わる情報を豊かに分かりやすく読者に提供している。 岸田内閣が決定し石破内閣が実行している「国家安全保障戦略」などの安保3文書と、そこに書かれた […]
〈2025.6月号 書評〉林 博史(著)「沖縄戦──なぜ20万人が犠牲になったのか」・・・天皇制という国家体制が押しつけた無慈悲な犠牲 評者:鈴木 耕(編集者)
自民党の西田昌司議員が、沖縄での講演会で述べた歴史改竄発言が、大批判を浴びている。 沖縄戦の実相をまったく学ばずに、いい加減な思い込みで、沖縄ヘイトに加担する政治家の底の浅さ。せめて本書を読むくらいの誠実さを持ってほし […]
〈2025.6月号 書評〉英 伸三(著)「老街茶館──英 伸三、中国江南を撮る」・・・茶館に集う中国庶民の姿を生き生きと捉える 評者:中村梧郎(JCJ代表委員)
上海西郊・朱家角鎮の倶楽部茶館に始まり、永昌鎮の南に至る地域の36軒を収めている。中国の文人墨客や庶民に愛された茶館ラオジエ(は、憩いの場であり、情報交換や商談の場でもあった。本書の写真には人の暮らしや人情が暖かく滲ん […]
〈2025.5月号 書評〉樋口英明(著)「原発と司法──国の責任を認めない最高裁判決の罪」・・・被災地の人々から学ぶ 痛みを伴う貴重な教訓 評者:松久保肇(原子力資料情報室・事務局長)
本書は著者である樋口英明元裁判官が、明快に原発の危険性を説く。彼は福井地裁による2014年の関西電力大飯原発3・4号機運転差し止め判決、同じく福井地裁による2015年の関西電力高浜原発3・4号機の運転差し止め仮処分決定 […]
〈2025.5月号 書評〉藍原寛子(著)「震災後を生きる13人の物語──フクシマ、能登、そしてこれから」・・・被災地の人々から学ぶ 痛みを伴う貴重な教訓 評者:坂本充孝(ジャーナリスト)
天災は故郷を壊わし、生活をなぎ倒し、心を打ちのめす。そんなとき人は、どうやって起き上がり、歩き始めるのか。東 日本大震災と能登半島地震。二つの災害現場を舞台に復興に力を尽くす13人の物語を、福島在住の著者が丹念に追跡す […]